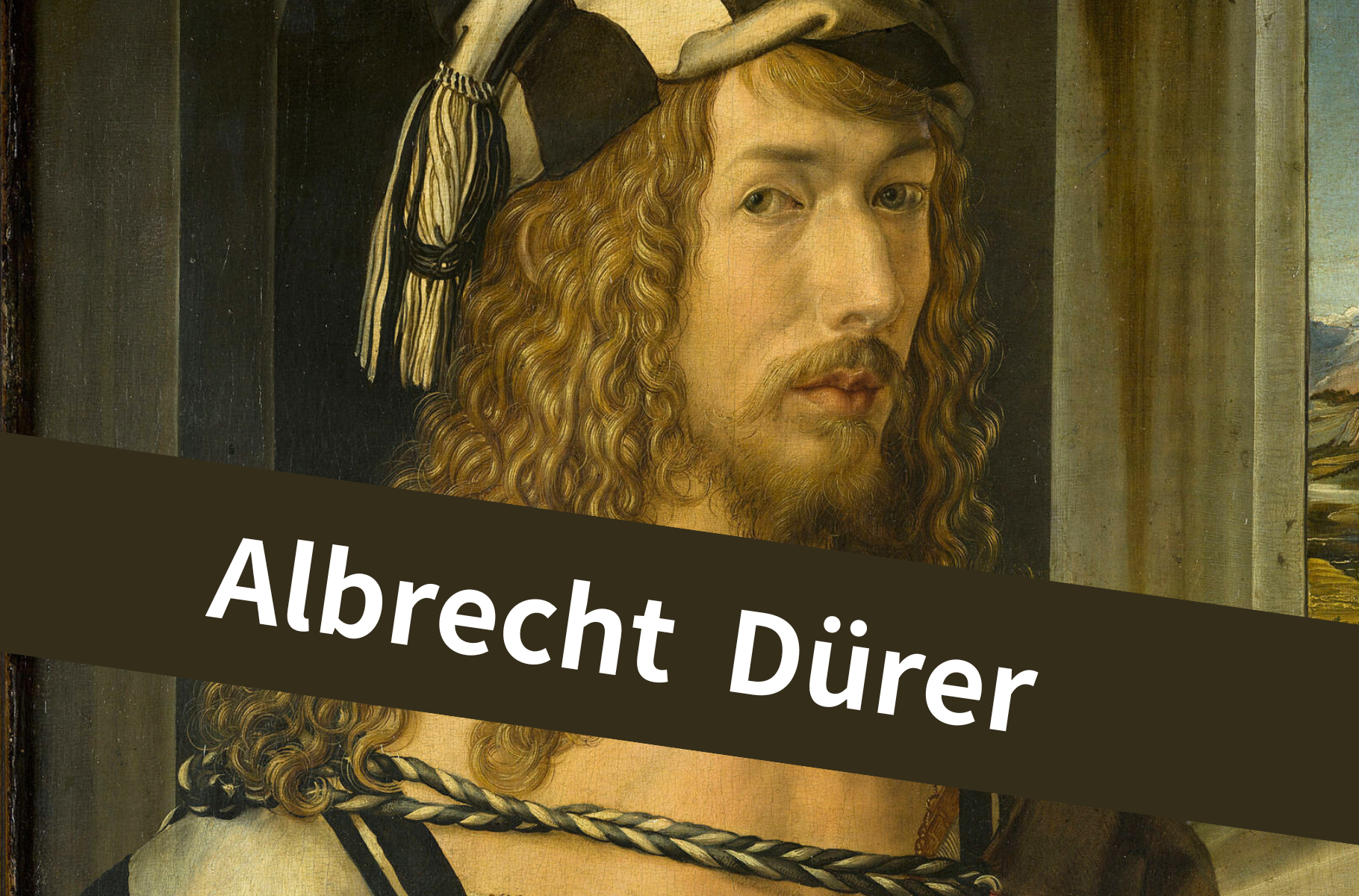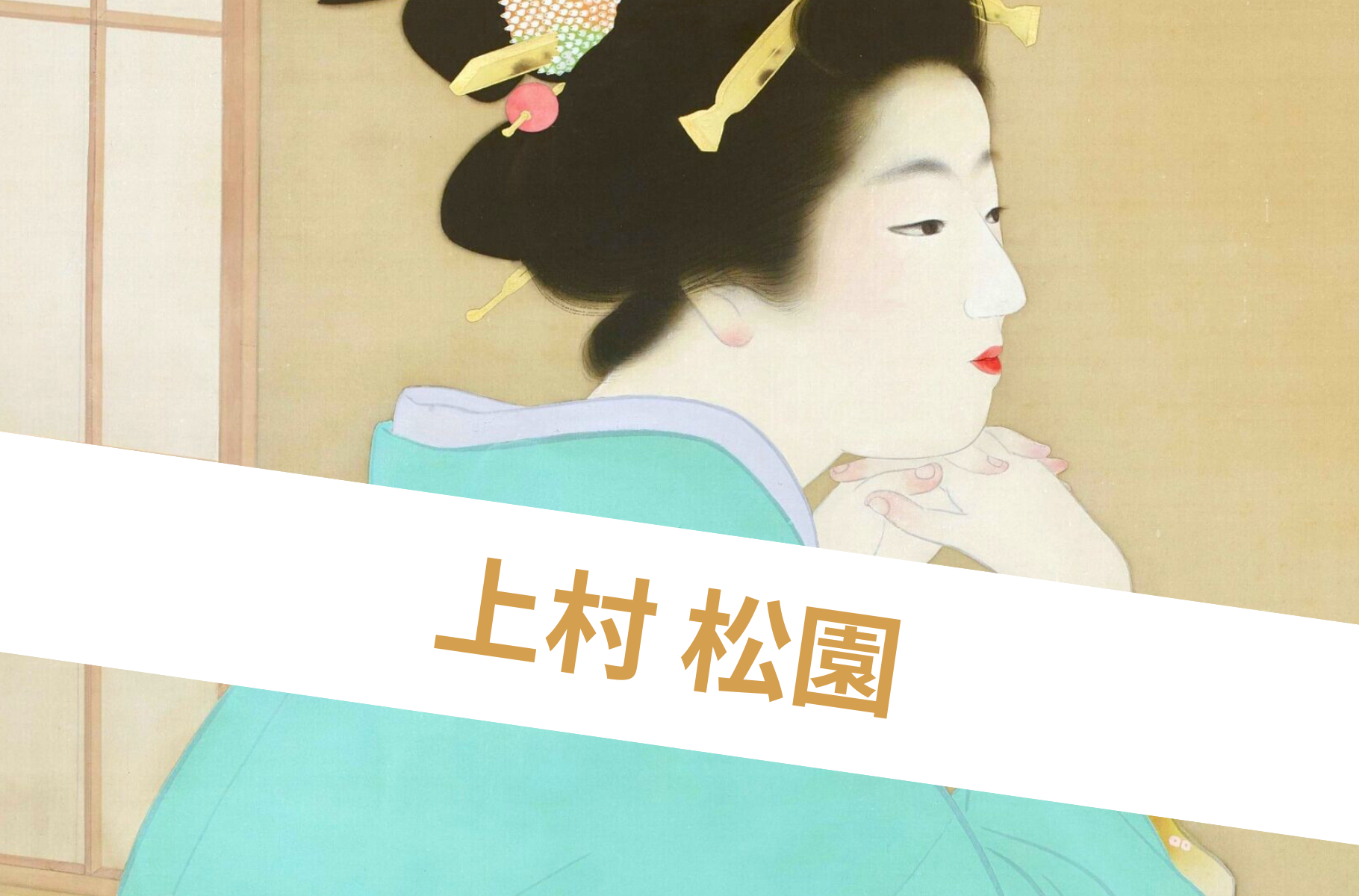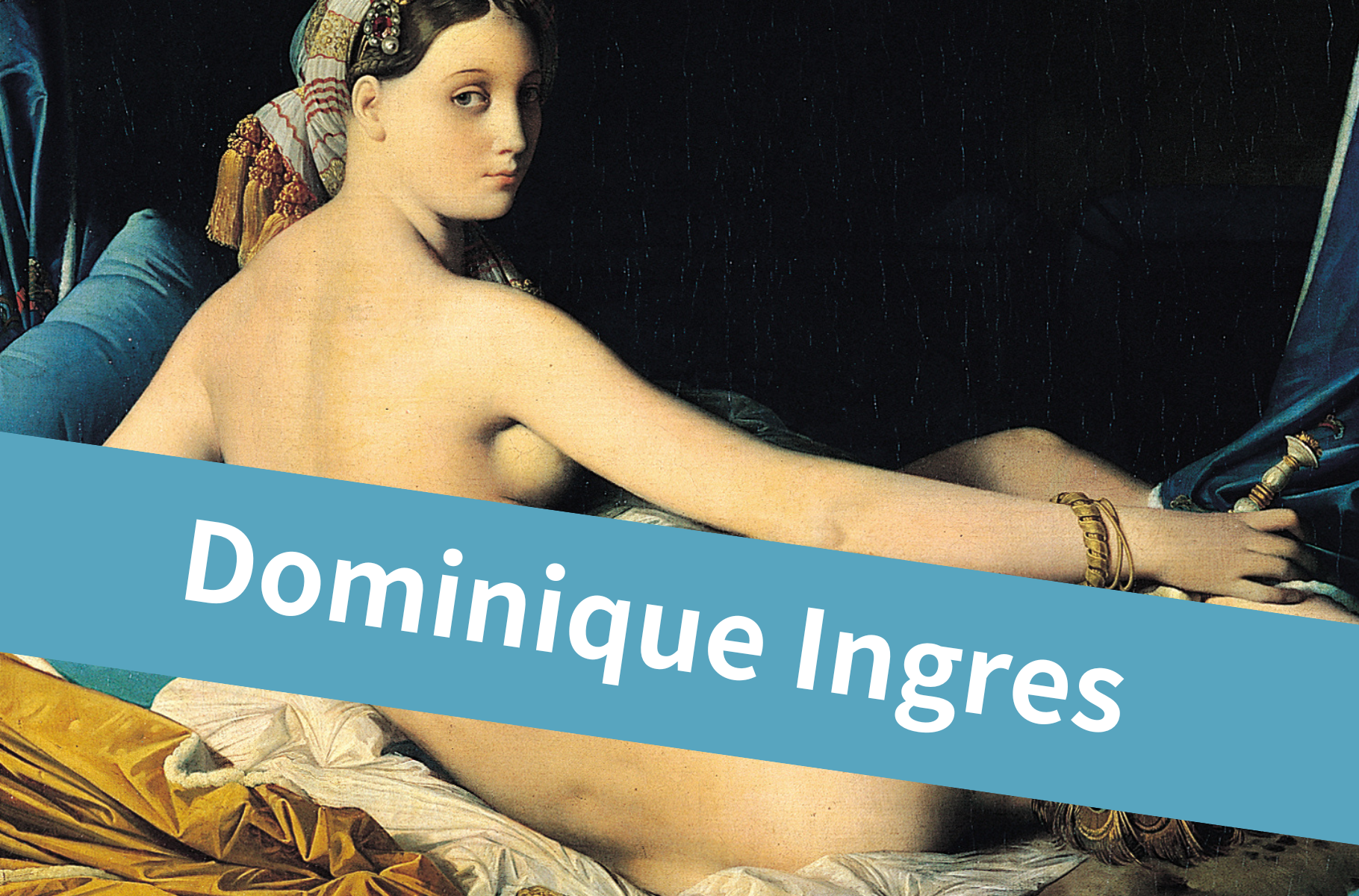光と闇の魔術師
レンブラント・ファン・レイン
レンブラントは今から約400年前、オランダのライデンという街で生まれました。なんと14歳で飛び級してライデン大学に入学。「法律家になってほしい!」という両親の大いなる期待とは裏腹に、入学して数カ月後には「画家になる!」と退学してしまいます。
でも、どうやら天はレンブラントに二物を与えていたようです。なんとなんと、まだ10代の若さで自身の工房を構えるほどの腕前を発揮するのです。

異教徒から石打ちされるステファノの殉教シーンを描いた『聖ステファノの石打ち』は19歳の時の作品。ステファノには眩しいくらいの太陽光があたり、それを見つめる異教徒たちは光を遮るように黒々と描かれています。光を描くには闇も描かねばならない。すでに光と闇の魔術師の片鱗が見て取れます。
レンブラントは25歳ごろから画商の仲介で肖像画の注文を受け始めます。当時の肖像画といえば「おすまし顔」が当たり前。団体さんを描く場合は前を向いて並んでいるという構図でした。今でいえば集合写真みたいなものですね。
でも、そこはさすがレンブラント。ただの肖像画では終わらせません。持ち味である光を巧みに使い、臨場感たっぷりの作品に仕上げました。

(マウリッツハイス美術館)
例えば、アムステルダムの外科医師会のために描いた集団肖像画『テュルブ博士の解剖学講義』。外科医の見せ場でもある解剖シーンを舞台にメンバーを描き、依頼主を大いに満足させました。この絵は評判を呼び、レンブラントは時代の寵児となります。

(アムステルダム国立美術館)
642年、絶頂期のレンブラントは代表作となる『夜警』を制作します。横幅が4メートルを超えるこの大作はコック隊長率いる自警団の集団肖像画。ところが、レンブラントは得意の集団肖像画で足をすくわれてしまったのです。
きっかけは依頼者たちからのクレームでした。「迫力と快活さを併せ持った素晴らしい作品なのに、なぜ」と思われる方も多いでしょう。でも、思い出してください。これはあくまでも「肖像画」なのです。なのにレンブラントは絵の光を追求し、迫力を優先したため、一人ひとりの顔の描き方に差が出てしまったのです、「相場よりかなり高い金額を分担したのに、なんでオレの顔は隊長に比べて暗くて雑なんだよ!」とがっかりした人が多かったのです。

ご覧の通り、顔に当たる光の具合や表情のきめ細かさなど、人によって大きな差がありますよね!
そんな訳で「レンブラントに依頼しても、たいした絵にはならない」という噂が広がり、肖像画の注文が激減してしまいました。
しかし、事態はそれだけでは収まりませんでした。このことが引き金となったのか、災難が次々とレンブラントに襲いかかってきます。愛する妻が出産直後に亡くなり、男女関係の泥沼に巻き込まれ、借金生活を余儀なくされ、投資に失敗して破産し…。寂しさと焦りが相まって、人生が負のスパイラルに絡め取られていたのかもしれません。

すべてを失い、無一文になった1659年に描かれた『自画像』は未完の作品ですが、窪んだ目から絶望の暗い光が放たれた傑作です。多くのものを失ったレンブラントですが、表現力だけは健在でした。無一文になって貧民街での生活を余儀なくされたレンブラントは、その生活ぶりをにじませたような暗い色調の中に深い思索を感じさせる、そんな作品を数多く残しました。
その後もさらに不幸な出来事が続き、後半生はまさに失意のどん底にいたレンブラントですが、生前からその名は国境を越えて広がっていました。後世の作家にも影響を与え続けたレンブラント。後にバロックの巨匠と称され、今でもオランダ国民の誇りとなっています。